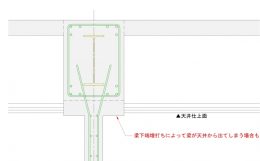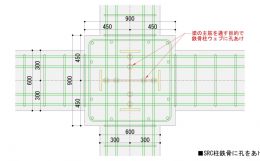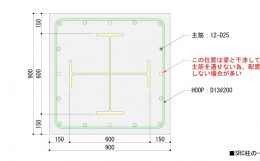前回は少し鉄筋の納まり検討についての話から逸れて、時間がない中で検討していく事になりがちな現状を心配してみました。
ここで私が建築業界の行く末を心配しても仕方がないのですが、色々と仕事をしながら見ていると心配になることもあるので、少し愚痴っぽい話をしてしまいました。
以前から気になっているのが、充分な能力と意欲を持っていると思われる新卒の方がすぐに辞めてしまう状況が現実として少なからずある、という点です。
理想と現実のギャップに驚いて辞めていく場合もありますから、辞められてしまう側にだけ責任がある訳ではありませんが…
建築関連の仕事をはじめて少ししか経っていないのであれば、当然失敗だらけになるのは当然で、それを受け止める余裕が企業になくなりつつあるような気がしています。
あまり教わっていない状態で仕事を進めて、当然の結果として上手くいかなかった時に誰もフォローしてくれない、という状態では人は育ちません。

何もかもが昔は良かったと言うつもりはありませんが、人の教育に関しては、そういった部分が昔はもう少ししっかりしていたような気もします。
もちろん昔はパワハラ的な事を考えるとあり得ないような事もあったので、どちらが良いかを比較するのは難しいですけども。
恐らく働く側としては「もう少しそうした余裕があれば良いのに」と思い、企業側としては「もっと意欲をもって猛烈に働いて欲しい」と思っている。
そんな感じなのだと思います。
どちらかが一方的に正解で、一方は全然間違っている、という訳ではないので、ある程度バランスをもった着地点が欲しいところですが、なかなか現実は難しいです。
…と、かなり話が散らかってしまったので少し最後にまとめてみます。
・建築関連の仕事を覚えるには知識に対する「飢え」が必要不可欠
・継続して成長するには当然意欲も継続していく必要がある
・ただし業務量の多さなどが現実としてあり意欲を保つのはなかなか難しい傾向にある
・結局は業務量と意欲のバランスを取りながら仕事をすることになる
仕事ですから楽にこなせる業務量で終わるはずはなく、ある程度頑張りが必要な業務量を与えられるのは仕方がないことでしょう。
しかしそれが過ぎると非現実的な業務量になってしまい、それをなんとかこなそうとする中で建築に対する意欲を失っていく、という流れになるのだと思います。
だからこそ、膨大な業務量があっても意欲を失わない人に価値がある、と言いたいところですが、それは完全に企業側の理論になってしまいます。
私もそうした超人的な人を何人も知っていますが、全ての人がそうである訳ではないです。
だから一般的な話をすれば、仕事と私生活のバランスをとる必要がある、ということになる訳です。
そのバランスは人によって色々ですから、自分なりの距離間をもって仕事にあたるしかない、というのが現実ではないかと思います。
とは言っても、もう少し余裕が欲しいというのも正直な気持ちだったりします。
このあたりの話は「これが正解」という確固たるものがありませんから、自分なりのバランス感覚を持っている必要があるのだと思います。
ただ、そうしたバランス感覚を持って仕事をしようとしても、対企業で考えると個人はあくまでも「雇用されて評価される側」なんですよね…
だからある程度のレベルまでは企業の要望に応える必要があって、個人の仕事に対する距離感はその要望に応えることが前提になってしまいます。
企業としても、社員全員にのんびりと自分のペースで仕事をされたら利益を出すことが出来ない、という思いがあるので、ある程度の要望があるのは当然です。
こうした話は結局着地点がなくなってしまうのでこのあたりで終わりにしておきますが…
企業に雇用されて仕事をするのも、企業を経営して利益を出し続けるのも、どちらもなかなかに難しいことですよね。