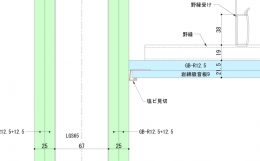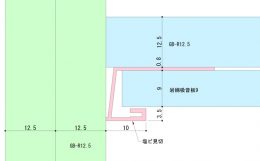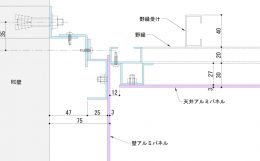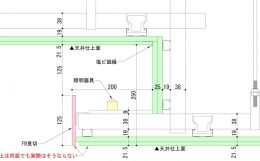しばらくの間ずっと廻り縁についてミリ単位の細かい話が続いていて、恐らく読んでいる方も疲れてくるのではないかと思います。
とは言っても納まり検討はこうした細かい話の連続になるのが現実なので、ここであまり細かくない適当な話をする訳にもいかず…
まあ納まりの話だから細かいのは仕方がないか、と思って読んで頂ければ嬉しいです。
ただ、こうした廻り縁関連の納まりは、現場で実際に施工する少し前に決める感じでもあまり問題はないので、どうしても後回しになってしまいがちです。
忙しい中でこうした検討をいつやれば良いのか、というあたりの話はちょっと難しい部分もありますが、一度意識をしてみた方が良いかも知れませんね。
施工者としては、廻り縁の納まりよりも前に、鉄骨や外部建具や内部建具など、事前に工場で製作をかける必要があるものに関わる部分の納まりを検討していく必要があります。
特に構造体である鉄骨の検討は細かいし、間違えると再製作など結構致命的な状況になったりするし、なかなかシビアな検討になってくる場合が多いです。
それを考えると、廻り縁は既製品なので注文すればすぐに届くし、天井仕上材も現場でカットするのでやはり既製品の天井で済むとう気楽さがあります。
だから後回しになってしまうのですが、それでも最終的な見え方に影響が出てくる部分でもあるので、どこかの時点できちんと方針を決めたいところです。
一度考え方を決めてしまえば、後はその方針で施工を進めるだけになるので、出来れば仕上げ工事をする前の段階が良いでしょう。
その段階で重要な部分の検討が終わっていて、時間にある程度余裕があるかどうかは、プロジェクトに関わる人数などによるとは思いますが…
天井仕上材の種類はそれほど多種多様にある訳ではないので、別のプロジェクトでも同じ納まりの方針を使うことが出来ます。
そう言った意味では、一度自分が良いと考える廻り縁関連の納まりを、納まり図集みたいな感じで揃えておくと良いかも知れません。
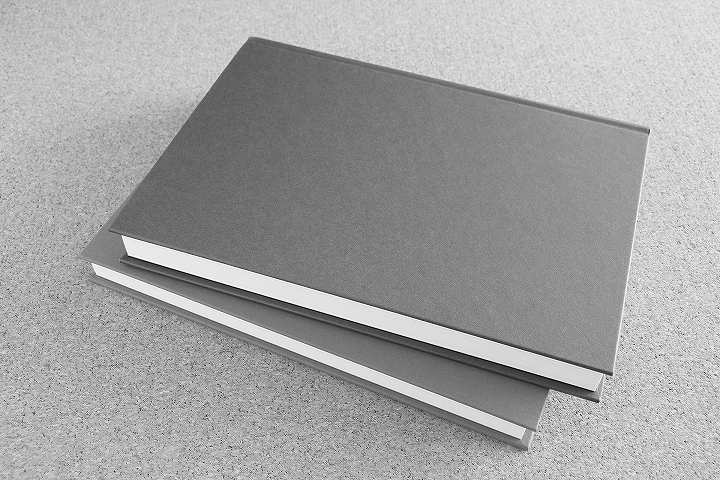
何度か違うプロジェクトで同じ部分の検討をしていくと「これは以前の納まりが使えるかも」と思うシーンが結構出てくることになります。
そうなると納まりの問題点や最終的な見え方などが既に分かっているので、思った状態と違うなどの問題が少なくなるというメリットがあります。
デメリットとしては「ワンパターン」の納まりになってしまい、もっと良い納まりがあるかも知れないのにそれを目指せない、という話があります。
ただ、例えば今回取り上げている廻り縁の納まりでは、それほど目新しい納まりがある訳でもないので、こうした部分は別にワンパターンでも良いのではないかとも思います。
そう言った意味で、過去の経験に基づいた納まり図集を持っておく事は、時間短縮や手間を省くなどの効果が期待出来るので良いのではないかと思います。
忙しいとなかなかこうした下準備のようなことは出来ないのですが、実際に作ってみると割と簡単に出来たりするものです。
これは意匠設計者でも施工者でも同様で、こうした納まりの検討をして「建物の完成形をどう見せるか」に関わる方であれば、こうした資料を自分で作っておくのも良いと想います。
手間がかかって面倒だからという事もあって、そうした資料を細かく準備しておくなどをする人は恐らくほとんどいないと思います。
だからこそ準備をしておく事に価値があるとも思うので、ぜひ一度自分の中の知識を整理する意味もあるので、納まり図集を作ってみることをお勧めします。
私がこうして細かい部分について説明しているのも似たような理由からで、やはり自分の中にある知識を整理するにはアウトプットが必要なんですよね。
ちょっと変な話になってしまいましたが、次回は天井がそのまま下り壁に取り合ってくる部分の納まりについて考えてみたいと思います。