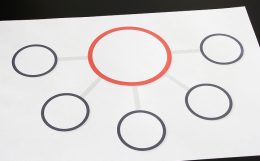前回はゼネコンとサブコンの関係や、ゼネコンの協力業者として工事を発注される企業について少し考えてみました。
建築現場においては、ゼネコンを指して「元請け企業」と呼び、サブコンや協力業者を指して「下請け企業」と呼ぶ場合があります。
お金を支払う側と受け取る側という部分で考えたり、方針を検討して決める側とその指示を実行する側という部分で考えたりすると…
元請けと下請けとの関係は必ずしも対等ではないという事になるのかも知れません。
ただ、コンビニで買い物をする側と店員さんとの関係も、やはりお金を支払う側とお金を受け取る側という事になります。
この関係も対等ではないにしても、そこまで立場に違いがある訳ではなく、別にお金を支払う側が偉いとかいう話では全然ありません。
時々そのあたりを勘違いして、店員さんに横柄な態度を示す恥ずかしい方を見かけますが、まあ世の中には色々な方がいるものです。
お客様は神様です
という言葉が割と一般的になっていますが、ここで指しているお客様というのは、歌を聴きに来たり演技を見に来たりする方の事です。
ステージに立って歌を披露する側の心構えとして、聞きに来られたお客様を神様だと思って全力で歌う、という気持ちを表している言葉なんです。
お金を払っている=お客様=神様 という事ではありませんので、そのあたりを勘違いして恥ずかしい思いをしないようにしたいものです。
ちょっと変な話になってしまいましたが、元請け企業であるゼネコンが下請け企業にとっての神様という訳ではない、という話でした。
このあたりを時々勘違いしている方はいますけど、まあこれは見ていて恥ずかしいものがあります。
もちろん施工を進める際の方針を示す役割を担うゼネコン側には重い責任がありますから、厳しく指示をする場合もあります。
しかしそうした話と上下関係の話は少し違うんですよね。
そうやって勘違いさせてしまう周囲の環境も良くないのですが、私がそこまで危惧してもあまり意味がないので、このあたりの話はこれで終わりにしておき…
今回から考えてみるのは、施工者が施工を進める際の基本方針についてです。
ゼネコンであってもサブコンであっても、施工者としては「設計図を基本方針とする」ということを前提に工事を進めていくことになります。
設計図は建物をどんな考え方で建てていくかの指針となる図面ですから、それを元にして工事を進めていく事は施工者として最も基本的な前提条件と言えるでしょう。
基本方針となる設計図で示されるのは、どのような方針で建物を造っていくかではなく、完成した建物がどのような形をしているか、という種類のものです。
それだけでは建物を建てるのに不充分ですから、施工者としては、そうした建物の最終形をイメージしながら「どのような手順と工法で建物を造っていくか」を考えていく必要があります。

建物をどのように造っていくのがベストなのかを一言で表すのは非常に難しく、また建物ごとに様々な条件がありますから、プロジェクトごとに必ず違ってくることになります。
そうした条件を考えてながら施工の手順を練っていき、それを現場で実際に実行していく事が施工者に与えられた役割になる訳です。
施工者であるゼネコンはそのあたりの知識や技術をたくさん持っています。
設計図はあくまでも完成形のイメージである訳ですから、それをベースにしながら建物をどのように効率よく造っていくか、という部分は施工者の腕の見せどころだと言えます。
その手際によって、建物を建てるプロジェクトが施工者として成功と言えるかどうかが大きく変わってくることになるので、当たり前の話ですが責任重大なんです。