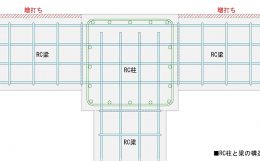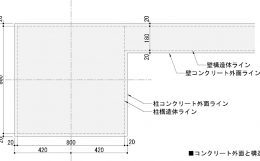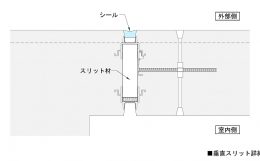鉄筋コンクリート造はその名前の通り、コンクリートと鉄筋を組み合わせた構造である、という結構当たり前の話を前回は説明してみました。
こうした一般的な話を「実はこうなんです」という感じで書くのは少し気が引けますが、最も基本的な部分を省略する訳にはいきません。
圧縮方向と引っ張り方向という異なる方向の力に抵抗する為に、コンクリートと鉄琴という異なる部材を組み合わせる、という考え方。
こうしたお互いの欠点を補い合う関係で構造体が構成されているというのは、非常に上手く出来ているな…と思ってしまいます。
今回はそんな鉄筋コンクリート造の中で、コンクリートを補強する役割を担っている鉄筋について少し考えてみる事にします。
鉄筋はRC造の納まりを語る為には欠かせない部材で、どのような形状をしているのか、というあたりの話は前回も紹介してきました。
鉄筋の太さや鉄の細かい仕様などによって色々な分類はありますが、大雑把な鉄筋のイメージとしては以下のような感じになります。

このような形状の鉄で出来た棒を鉄筋と呼び、必要な構造体の強度などに合わせて様々な太さの鉄筋が規格品として製作されています。
表面に凹凸があるのはコンクリートとの付着を良くするという狙いがあって、凹凸がないものを「丸鋼」と呼び、凹凸があるものを「異形棒鋼」と呼びます。
表面の形状にフォーカスしてみると、まずはこれが丸鋼になります。

そしてこちらが異形棒鋼。

同じ鉄筋とは言っても、表面の形状によって見た目は非常に大きく変わってくる事になる、というのが上記の写真では分かると思います。
コンクリート内に設置する鉄筋として、丸鋼と異形棒鋼のどちらが構造的に強度を持っているかというと、当然ですが異形棒鋼になります。
表面に凹凸がない鉄の棒よりも、凹凸がある鉄の棒の方がコンクリートにしっかりと絡みますから、補強材としてはやはり異形棒鋼が採用される、という考え方です。
異なる力に対してそれぞれの部材で対応するとは言っても、まずは鉄筋とコンクリートがしっかりと密着していないと、強固な構造体とはなりませんから。
そのあたりを考えてみると、構造体として利用しない丸鋼を「鉄筋」と呼ぶのは少し違うのかな、という感じになってきます。
一般的に「鉄筋」と言えばそのまま異形棒鋼を指している事がほとんどで、あえて鉄筋として丸鋼を採用する建物というのは恐らくありません。
だからわざわざ「異形棒鋼」という表現を使う機会もあまりなく、単純に「鉄筋」と言えば異形棒鋼の事を指している、という感じになっています。
こうした鉄筋とコンクリートを組み合わせた建物の構造は、いくつかのパターンに分かれる建物の構造の中で最もオーソドックスでわかりやすい構造ではないかと思います。
もちろん、いくらRC造が分かりやすくて一般的な構造だからと言って、それがそのまま簡単な納まりになる訳ではありません。
だから無責任に「鉄筋コンクリート造は分かりやすいです」という表現をするのは、あまり良くないし正解ではないという事になってしまいます。
そうはいっても、恐らく鉄骨造(S造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)に比べれば分かりやすい、というのは事実でもあります。
このあたりの話は後ほど詳しく説明をしていきますが…
やはり現場で加工する部分が多い鉄筋コンクリート造は、比較的分かりやすくて覚えやすい構造になっているのではないかと思います。
何かを覚える際には比較的簡単な部分から入るのが良いので、建物の構造としてまずは鉄筋コンクリート造の基本的な納まりから覚えてしまう方が良いのではないかと思います。